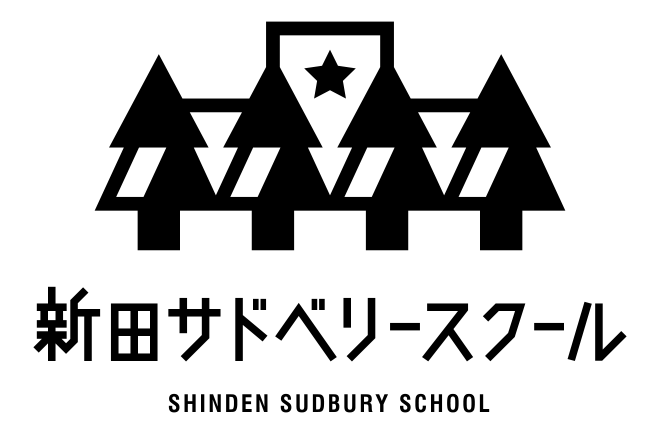生産から加工販売までを6次産業と表現したりしますが、昨日は自分たちで苗から育てたもち米を使って、餅つきをしました。
僕は私生活でお米や野菜を栽培していますが、常々自分ところで作った作物は自分ところで消費するのが一番気持ちが良いと思っています。手塩にかけて育てた作物を売って現金にすると途端になんだか味気無さを感じてしまうのです。
今回のもち米も、田植えから、夏の暑い時期の草取りから、稲刈り、稲木干し、脱穀、籾摺りといくつもの手作業を経てもち米になりました。
(「冬にお餅つきが出来たら楽しいね」というHちゃんの発言からもち米を少し植えました。)
お米作りメンバーに限らず、みんなで楽しんだ餅つきでしたが、お米作りに携わったメンバーは特に口にする餅の味以上のものを味わったんじゃないかと想像します。
前置きが長くなりましたが、餅つきをしました。
週に1回の火曜日はなおみさんスタッフの「季節の手作りクラブ」の日。
その日に餅つきをしました。
もち米は新田サドベリースクールで春から栽培していたヒメノモチです。
栽培して出来たお米はそれらの作業に携わった人が携わった分だけ持ち帰ることにしていましたが、一部新田サドベリーにも置くことにしました。
その一部置かれたもち米で今回は餅つきをしました。
 なおみさんの家から餅つきセットを一式をお借りして、本格的な餅つきです。
なおみさんの家から餅つきセットを一式をお借りして、本格的な餅つきです。
かまどを使って、薪でもち米を蒸しながら、蒸しあがったら杵と臼でついていきます。
姫路セントラルパークのジェットコースターのとき同様、「餅つきしたことなーい。」「はじめて~」って子が結構いました。「地区の行事でしたことがある。」という子もいました。
僕は、下手でも平気、まずは自分でやってみることが大事だと思っています。
自分で主体的にやったこと、作ったものというのは多少不格好であっても、とても貴重な体験になると思います。
まず、自分でやってみて、「やってみたら出来た。」とか「やってみたら意外と難しかった。」→上手にやっている人はどうやっているんだろうと観察したりとか、そういう時間ってとても大切です。
主体的に動いたときに得られるものはたくさんあるように感じています。
この日も子どもたちは積極的に外に出てきて参加していました。
「私もやりたい」「次は私」と順番についたり、手水したり、ついた餅を丸めたり。
どうしたら上手に出来るかな、どうしたら杵で手をついてしまうようなことが無いかな、とか色々なことを思考しながらやっていたのではないでしょうか。
小学生も3,4年生くらいになると、自分たちで餅つきも出来てしまうんですね。
幸い誰の手も杵でつかれることなく作業できました。
メンバーを変えながら、疲れたら交代しながら、4升の餅をつきました。
ついたら丸めて、きなこ・あんこ・砂糖醤油・大根おろしなどをお好みでトッピングしながら食べました。
お餅とは別に作った、お味噌汁(サドベリー4年みそ)も大好評で温かいみそ汁に、つきたてのお餅にと贅沢な時間でした。
大勢でワイワイしながら出来たこと、手を動かしながら出来たこと。
良い時間でした。
季節の手作業って良いなぁって僕は個人的に好きなんですが、子どもたちの中にも何かしらのものが残ったら良いなと思いました。
餅も好評で「うまい うまい」と4個も5個も食べる子どもの姿がありました。
お持ち帰りの分も、翌日のおやつの分も出来ました。
薪ストーブであぶりながら食べてもうまいんだろうなぁ。
※ついつい、もち米が熱いうちにつかないと餅にならない(粒が残る)とか思うので、のんびりついている(ように僕には見える)のを見かねて「僕次ついても良い?」と入ろうとするとYちゃんが「他の子も並んでいるんだから、洋ちゃんもちゃんと並ばないとダメだよ。」と注意されました。
そのYちゃんの発言が嬉しかったので忘れないように書き留めておきます。
きちんと「100点満点」の餅を目指すのも良いけれど、きちんと「順番を守って、みんなで餅つきを楽しむ・味わう」というのも大事。
僕が近くにいながら「熱いうちにつくんだよ。最初臼に移したら、すぐにもち米をつぶすんだよ。最初は優しく、手早く、後半は力強く。」なんて横から口出ししているのをきっと子どもたちは十分聞きながら、その中で自分たちで餅つきに向かい合っていたんじゃないかな。
それぞれを尊重しながらあれるこの場っていうのは本当に貴重だなと感じました。
【文 長谷洋介】